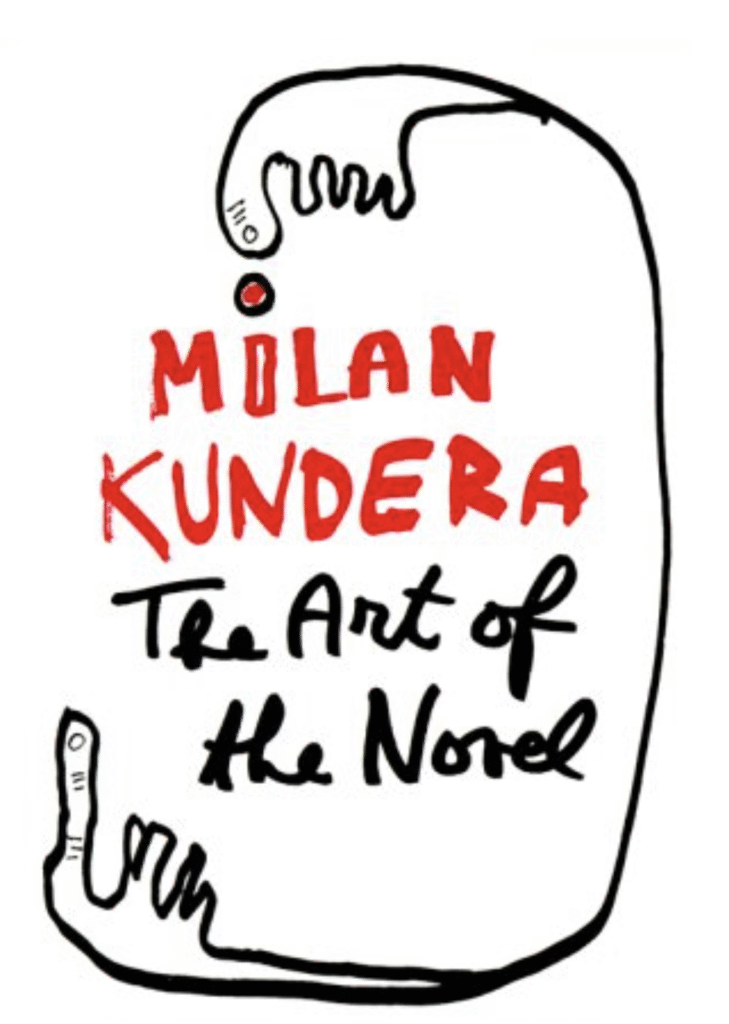
「なぜ我々は毎秒10ビットでしか生きられないのか?」という仮説についてZheng & Meister (2024)は、過去100年に渡る人間の認知能力に関する研究を網羅的に捉えたレポートを発表しました。
AGIやASIの誕生への期待や、これらを疑問視する意見などにも多くの示唆を与える内容になっています。
ちなみに「存在の耐えられない遅さ」(The Unbearable Slowness of Being)は、チェコスロバキアを代表する文豪であるミラン・クンデラの『存在の耐えられない軽さ』(The Unbearable Lightness of Being)からとったものでしょう。
以下は、レポートについてまとめてもらったものです。
序論 (Introduction)
人間の脳が処理できる情報の速度には驚くべき上限があることが近年明らかになりました 。カリフォルニア工科大学のJieyu ZhengとMarkus Meisterによる最新の研究(Neuron誌, 2024年12月オンライン公開)では、人間の意識的な情報処理のスループットは約10ビット/秒に過ぎないと報告されています 。これは、視覚や聴覚などの感覚系が1秒間におよそ10億ビット(1ギガビット)ものデータを環境から取得しているという事実と比べて、実に1億倍以上も遅い値です 。この「存在の耐え難い遅さ」とも言うべきギャップは、人間の認知処理速度の限界と神経情報伝達の効率について根本的な疑問を投げかけます 。なぜ私たちの脳はこれほどまで低速の情報処理しかできないのか? 本稿では、Zheng & Meister (2024)の論文を中心に、この疑問に対する主張・知見をまとめ、その実験手法と理論的背景を詳細に解説します。また、この研究と密接に関連する主要な先行研究を整理し、それぞれの内容・方法・結論の共通点や相違点を比較検討します。最後に、人間の情報処理速度の限界や脳の情報効率についての深い考察を行い、今後の研究の方向性を示します。
背景 (Theoretical Background)
情報理論と脳科学の接点: 人間の認知能力を「ビット/秒」で定量化するアプローチは、情報理論創始者クロード・シャノン以来の試みに端を発します 。シャノンが提示した情報エントロピーの概念により、メッセージの不確実性や情報量をビットで測ることが可能になり、20世紀中頃から心理学者や神経科学者は人間の感覚・認知過程にこの枠組みを適用してきました 。たとえば、Hickの法則(1952年)では、選択肢が増えるほど反応時間が対数的に伸びることを示し、人間が単位時間に処理できる情報量(情報獲得率)に上限があることを示唆しました 。同様に、Fittsの法則(1954年)では、人間が手や指を動かして目標を指し示す際の速度と精度のトレードオフから、運動系の情報処理率が約10ビット/秒に収束することが示されました 。さらに、シャノン自身も英語テキストの統計構造を解析し、英語のエントロピーは1文字あたり約1ビット程度しかない(つまり英語文には大量の冗長性がある)ことを報告しています 。これは、人間がタイピングや会話で伝達できる情報率の理論値がおよそ数十ビット/秒程度に限られる可能性を示唆するものでした。実際、平均的な音声会話の情報伝達率も言語を問わず数十ビット/秒程度に収束することが近年報告されています 。
「7±2」と注意のボトルネック: これら情報理論的分析と並行して、心理学分野では人間の認知容量の限界が古くから議論されてきました。有名なジョージ・ミラーの「マジカルナンバー7±2」は短期記憶に保持できる項目数の限界を示しましたが、これはストック(容量)の問題であり、本研究の焦点であるフロー(単位時間あたりの処理量)とは異なります。しかし、Donald Broadbentによるフィルターモデル(1958年)やその後の注意研究は、人間の認知処理が一度に一つの情報流しか扱えないという単一チャネル仮説を提唱しました 。すなわち、感覚系から膨大な情報が並列に入ってきても、注意のボトルネックによってごく限られた情報しか同時には意識に上らないという考え方です  。実験的にも、二つの課題を同時並行で行わせると片方の処理がもう一方を妨げて遅延が生じる(デュアルタスク干渉)ことが報告されており 、人間の中枢処理は基本的に直列(シリアル)であるとの結論が支持されています。このように「一度に一つのことしかできない」という現象は、日常的な実感とも合致するものですが、脳内で何がそれを制約しているのかというメカニズムについては、長らく明確な答えが得られていませんでした  。Zheng & Meisterの研究は、この古くて新しい謎に情報理論と神経科学の両面から再挑戦したものと言えます。